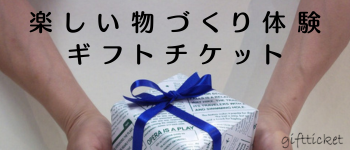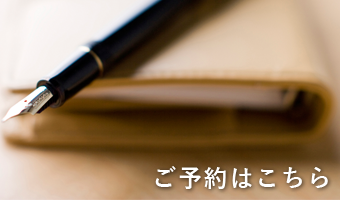粉引きの器制作を 今回行なっています。粉引きは 焼き方で 色が変化します。
これまで何度か 行なってきましたが そのつど その窯によって変わるのが粉引きです。あなたも偶然の美を追求してみませんか。


師楽陶芸教室の器特集
他では出来ない粉引きの器特集・・9月1日~10月20日まで 作る物は自由に出来ます。
ここでは片口を紹介しています。
 ※ 電動ろくろで器を挽く
※ 電動ろくろで器を挽くあなたも今回 電動ろくろに挑戦して見ませんか。意外と難しく 面白いのが電動ろくろでの器つくりです。
 ※ 電動ろくろで削る
※ 電動ろくろで削る電動ろくろでは 作る事も削ることも電動ろくろで行います。回転している器をこけしを 削るように形を整えていきます。
 ※ 口を取り付ける
※ 口を取り付ける片口は 小鉢として使うことも多く注ぎ口としての機能が無いものも多くあります。注ぎよい口は 口先を少し下に下げることで 流れがよくなります。
 ※ 粉引きは 生にかける。
※ 粉引きは 生にかける。粉引きは 白化粧を 形を整え終えた器がまだ 生の状態のときに 流しかけます。その際 掛け終わりすぐに 5分ほどドライヤーで乾かすことが重要です。
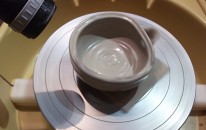 ※ ドライヤーで器を乾かす。
※ ドライヤーで器を乾かす。白化粧を まだ柔らかい粘土に掛けるため そのままにしておくと 崩れて壊れてしまいます。 早めにドライヤーで乾かすことで 形を維持することが出来
崩れることがなくなります。
師楽ではこの夏 多くの方に 陶芸を楽しんでいただきました。あなたも残り少ない夏の 思い出に物作り体験をして見ませんか。